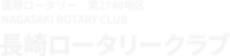被爆80年に思うこと ーーーー朝長 万左男君 (8月7日)
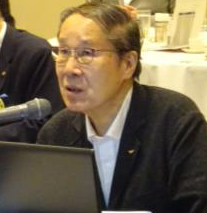
世界の核情勢が核戦争に向かって動きつつある。ここ10年の核軍縮の動向は反動的である。NPT(核不拡散条約)とTPNW(核兵器禁止条約)の2つの国際条約が成立して、その中で加盟国は核軍縮と究極的核廃絶を約束している。しかし実際の国連の会議の場においての核兵器国の行動は真逆であり、むしろ核軍拡の方向性さえ出てきている。特筆すべきは、6月に発表された英国の労働党政権の首相であるスターマー氏の発言である。
これまで英国は9つの核兵器国の中では最も誠実に核軍縮を推進してきた。特に空軍の核ミサイルを全廃し、潜水艦搭載型のみに限定するところまで進んでいた。ところが6月の声明で突如、ミサイル搭載潜水艦の数を増やすととともに、空軍に米国の核搭載戦闘機を輸入して攻撃能力を高めることを発表したのである。これは明らかに現在進行しているロシア・ウクライナの戦争において、開戦時から数回にわたってプーチン大統領の核兵器を使用する可能性を示唆する発言によって、一挙に西ヨーロッパのNATO諸国の警戒感がたかまったことが背景となっている。すでに北欧のスウェーデンとフィンランドがこれまでの中立を守る国策から離脱し、NATO加盟国となったことが、前段階としてあった。
またフランスのマクロン大統領も自国の核兵器をNATOの希望国に核の傘として提供できることを発表した。ウクライナ戦争の帰趨次第ではロシアが核兵器使用に踏み切る可能性があるため、世界の核情勢は極端に悪化してきているのである。もちろんそう簡単にロシアが核使用に踏み切る可能性は極めて低いと思うが、世界が核戦争を想定しつつ、自国の核政策を強化し始めていることが怖いのである。
アジアでもインドとパキスタンの核保有国の戦闘状態がカシミールで再発しており、将来が危ぶまれる。北朝鮮の核の脅し政策は全く変化なく推移している。日本においてはこれまで国政選挙の立候補者が日本の核武装を主張することなどは全くなかったが、突如某政党の候補が主張を展開したことは、世界の核情勢の変化に刺激されたものと 思われるのである。米国の核の傘に守られている日本の核政策に飽き足らず、自ら核兵器を保有することを考える政党が現れ、しかも得票数を伸ばし、議席の増加につながっている。これは国民の中にもこの政党を支持し、その核政策の主張を支持する国民が存在することを意味する。日本の若者世代の中にもこのような日本の核武装論が出てきていることはすでに知られている。
原爆被爆者の長年にわたる核廃絶運動によって、これまでは核兵器の使用はタブーとされ、核兵器国もその規範を遵守してきたと信じられてきたが、ここにきてこの規範がにわかに怪しくなってきたのである。昨年12月10日の日本被団協のノーベル平和賞受賞は、ノルウェーのノーベル賞委員会の現在の核情勢への危機感の表れとみなすことができる。先週、被爆者に核のタブーを核兵器国に訴えることをフリードネス委員長が来日して要請されている。今後世界の核意識がどのように変化していくか注視する必要がある。