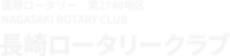「安心してお金をつかえるように するために」ーーー日本銀行長崎支店長・伊藤 真会員(10月23日)

中央銀行の始まりは15世紀頃と言われています。さまざまな国の貨幣で受け取った貿易代金を効率よくやり取りするためにヨーロッパ各地で設立された銀行が、中央銀行の始まりです。後の「銀行の銀行」に繋がる業務が出発点とされています。 19世紀になり銀行券の発行やお金の貸出が認められ銀行券の発行などにより銀行の経営が不安定にならないように、お金の価値を安定させたり流通量を調節したりする仕組みが同時に導入され中央銀行が世界に広まりました。日本も、西南戦争後の激しいインフレに対処させるため、中央銀行を1882年(明治15年)に設立しました。日本銀行の当初の業務は、「銀行の銀行」の業務、国内の銀行制度の整備でした。日本では、「政府の銀行」の業務も中央銀行の業務とされました。
「銀行券の発行」の開始は、国内のインフレが落ち着き始めた開業3年後です。 同時に、銀・金との交換を保証してお金の価値を安定させる兌換制度を導入しますが、1931年以降は、これを事実上停止し、銀行券の流通量を管理する金融政策の役割が大きくなります。日本銀行は、5000人弱の職員を、国内の32支店、14事務所、海外の7事務所に配置しています。長崎支店は、29番目の支店として1949年に開設され、発券銀行、銀行の銀行、政府の銀行の業務に加えて、当地の経済調査や統計の作成、広報活動を行っています。
現在、日本銀行が行う「銀行の銀行」 の業務では、480以上の金融機関から預金を預かり、1日に平均8万件超、約235 兆円の資金のやりとりを行っています。「発券銀行」の業務は、お札の流通残高は、2023年度末で約120兆円となっています。低金利が続いたこの25年間で倍増し、経済規模の20%超に上昇しています。この25年間、物価が上がらない状態に対応するため、 金融緩和策が講じられてきました。その 結果、日本銀行のバランスシートは、25年間で9倍となる729兆円となりました。銀行券の発行残高が倍増し、長期国債のほか、ETFやJ-REITなどのリスク性資産が増加しました。現在、物価が上昇局面に 転じ、金融政策は、伝統的な金利操作に 移行し、リスク性資産の残高を少しずつ 縮小させています。また、日本銀行では、消費者物価指数の上昇率が「2%」となることを目指しています。今後、物価上昇の主因となっている食料品価格が低下し、2027年に目標の2%になると見ています。日本銀行は、人々が安心してお金を使えるようにするために業務を行っていきます。